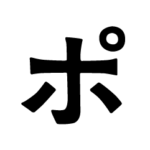2024.10.8
「本の街」京都が、さらにワンステップ、進化を遂げつつあるかもしれない

編集者
噂の広まり

この記事を書いた人
嶋田翔伍(しまだ・しょうご)
「必要な時に、必要な人に必ず届くのろしのような本作りを。」を掲げるひとり出版社・烽火書房(ほうかしょぼう)代表。堀川五条の路地にて新刊書店hoka booksも運営中。京都市生まれ京都市在住。近頃は改めて、本の周辺文化をはじめ京都の街へ強い関心を寄せている。
2024年になってからやたらと耳にする「京都市内に新しい本のお店ができた」という噂。それも一店だけではない。京都にはもともと恵文社一乗寺店やホホホ座、誠光社と、その店をめがけて京都旅行したくなる本のお店がたくさんある。古本文化も根付いていて、有名な古書店も多い。
筆者も小さな書店を運営しているため、本屋情報は普段から収集しているが、同じくらい閉店のニュースも聞こえてくる。本屋といえば、居心地のよい夢の空間というイメージがあるけれど、長く続く場所をつくるのは簡単ではない。
ところが、今年に入って開店のニュースを聞いた店は一味違う(気がする)。その秘密を探ることで、みなさんに「わざわざ訪れてみたくなる場所」を新たに紹介できるかもしれない。文化的なスポットとして有名な左京区だけでなく、上京区や北区などさまざまなエリアで「本のカルチャー」が花開きそうな噂に誘われて、今回は3つの場所を訪れることにした。
1. 「自分たちが取り扱う意味のある本」を届ける―余波舎 / NAGORO BOOKS
新刊と古書を扱うバランス感覚

はじめに取り上げるのは、京都市上京区の大宮寺之内にある書店・余波舎(なごろしゃ)。知る人ぞ知る名喫茶店「西陣ほんやら洞」のあった建物の2階に、2024年1月にオープンした。1階奥にはイタリアンレストランがあり、吹き抜けのエントランスから2階にあがる。近隣の穏やかな雰囲気によく馴染んだ気持ちの良い書店空間だ。店主は涌上昌輝さん、佐光佳典さんのふたり。チェーン型の書店ではなく、いわゆる独立系書店と呼ばれるお店だ。
店内を見歩き、話を聞いて見えてくる余波舎の特徴のひとつは、新刊と古書のバランス。どちらもたくさん並べられているのが見てわかる。新刊書店が少しだけ古書を並べる、古書店が少しだけ新刊書を並べる、といったことはあるにはあるが、余波舎の本棚のバランスは珍しい。

一見すると大差ないように思われる読者もいるだろう。けれど、実は案外勝手が違う。新刊書を扱うにあたっては、どんな書籍が登場したか、最新の出版情報に日々アンテナを張っておき、取次と言われる中間卸に発注を繰り返す。売れそうなら、同じ書籍をたくさん仕入れたり、販売状況を見ながら再度発注したり。涌上さんの言葉でいうと「流行を追い続ける」仕事だ。一方で古書店の仕入れは、古書市や古書店、店舗での買取を通して、一点ものを見つけ出す仕事だ。何を見つけられるかは確かな目利きと時の運に左右される。新刊と違い価格も店舗側で決めるので、ちゃんと利益が出るようにしつつ、これなら買いたいと来店者が思えるような塩梅の価格を設定する。同じように本棚に並ぶ本でも、仕入れから販売時の売り方まで何もかもが違っている。両方を取り扱うのはメリットもあるが、なかなか難しい。
涌上さんは長く京都に暮らしている。四条河原町のマルイにあった「フタバプラス 京都マルイ店」に勤めたあと、一乗寺の名物書店として知られる「恵文社」に移り2023年まで勤めた。チェーン型の大手書店と独立系書店のどちらも経験した書店員。そして、共同店主の佐光さんは「町家古本はんのき」で古書の販売をしてきた経験をもつ。新刊と古書の交わる棚づくりはこうしたふたりのキャリアから実現している。
コントロールできないことに付き合う
「近頃、独立系書店がたくさんできていて、本屋同士お互いの選書や店の雰囲気を横目で見てるわけじゃないですか。本棚を見れば品揃えも真似できるから、差別化が難しい」。課題意識をもとに、選書において気をつけてているのは「余波舎が取り扱う意味がある本かどうか」。だからこそ先述の古書の取り扱いやユニークな特集コーナーが生まれたのだろう。香港で出版された本を数多く仕入れているのもその一つ。近頃アジアの出版ムーブメントに注目が集まっていることは筆者も知っていたが、それでも知らなかった本がたくさん置かれていた。あまり日本には輸入されていないが、香港ではカルチャーの一端を担う雑誌社の本もあるという。これは涌上さんの家族が香港に明るいことから実現したラインナップであり他の店にはなかなか真似できないコーナーの一つだろう。
古書の仕入れはせどりや買取が中心なため、いつでもどこでも同じ仕入れができる新刊書とはまた異なる世界。「お客さんが持ってくる商品をこっちで選べないですよね。コントロールできないことに付き合っていくと、店のおもしろさに繋がるんじゃないかな」と涌上さん。なるほど、余波舎の本棚の豊かさは、自生する植物たちのように、コントロールの外側で育っていくのかもしれない。

「新刊書を見にきたお客さんが見たことのない古書を手に取ってくれたり、古書を見にきたお客さんが新刊書を知ったり。そういう思いがけない出会いをつくれたらいいですね」という涌上さんの言葉は印象的だ。「自分たちだからこそ取り扱う意味がある本」を選ぶのは簡単なことではない。筆者自身も書店を運営しているからこそその難しさがよくわかる。涌上さんもこれまで培ってきた経験をもとに日々トライアルアンドエラーを繰り返し、余波舎ならではの滲み出るような個性を模索している。
2.本とのかかわり方を増やすコミュニティ―一乗寺BOOK APARTMENT(シェア型書店)
売る人、買う人、もてなす人。三者が交わるコミュニティ

次に訪れたのは、京都市左京区の一乗寺BOOK APARTMENT。2024年7月にオープンしたばかり。近所には、恵文社をはじめマヤルカ古書店やアリバイブックスなど数多くの本のお店が存在する。そんな本と文化の街で開店した一乗寺BOOK APARTMENTは、新刊書店でも古書店でもない「シェア型書店」。シェア型書店は「アパートメント」の言葉が指す通り、まるで部屋を借りるかのように、個人が本棚の一区画をレンタルし小さな本屋を開店するような形式で運営されている。同店では第一期として45ブースが貸し出され、あっと言う間に、ほぼ全ブースが埋まったというから驚きだ。
どんな人たちが借りているのだろうと棚を覗いてみると古書店顔負けの選書のブース、ZINEや詩集などの制作者、伝えたいメッセージを選書に乗せたコンセプトのあるブース、著名人のブースなど、賑わう本棚に「住む」人たちの幅がとても広いことが見て取れる。店に伺った際には、出店者のお一人が机を使って、販売する本の準備やポップの作成も行っていた。こうして交流も生まれるのだろう。
店主は北本一郎さん。新聞記者として東京や名古屋で長年勤めた後、学生時代を過ごした京都に戻ってきたという。一乗寺BOOK APARTMENTのルーツは、東京のシェア型書店である「西日暮里BOOK APARTMENT」。北本さんはもともと同店で本棚を借りていて、シェア型書店の魅力を強く実感。自分も開店するなら同じ形式を、と決めた。許可を受けて「BOOK APARTMENT」の名前を冠し、本棚も同店の設計者に依頼したというから、その意志を広げる思いを強く感じる。長い間スナックとして使われていた一軒家を改装した同店には簡単なキッチン設備もありコーヒーやお酒を楽しめる。
「元々僕の身の回りには、本好きの人たちがそんなにいなかったんですよ。でもここで出店してくれる人もお客さんもみんな本が好きな人たちばかり。こんなに好きな本のことを語り合う時間はこれまでなかったです」と北本さん。店にやってくるお客さんと、そしてそこを利用する出店者たちと、店主の北本さん。三者が交わり、あたたかなコミュニティをつくり出す。
一歩踏み込んだ本との付き合い方
北本さんの実感するシェア型書店の魅力はそれだけではない。商品として日々品揃えが変化していく一般的な書店と違い、シェア型書店に並ぶ本は「誰かの愛読書」であることが多い。「31cm角のブースは、それぞれのオススメを紹介する『メディア』なんです。時には出店者さんから直接その魅力を教えてもらうこともありますし、おもしろいかたちで本と出会えます」と語る。本そのものが持つ魅力に加えて、自分がその本に出会うまでの物語が付加価値となり、愛読書が増えていく感覚を得られるのだという。
出店者が殺到した理由の一つとして、本が好きな人たちの「熱気」があるという北本さん。「例えば文学フリマが人気なことも近いと思うんですけれど、今の時代、本を読むだけじゃなくて、もう一歩踏み込んだ関わり方をしたいとみんなが望んでるのを感じます」。文フリこと文学フリマは、来場者数が多いことはもちろん出店希望者もかなり多い。それだけ多くの人が「本をつくりたい」ということ。シェア型書店の場合は、ZINEのつくり手が直接販売したいとか、お気に入りの本を選書して人に魅力を伝えたいとか、本好き同士で語り合いたいとか、そういう一歩踏み込んだあり方への欲求が集まるのだろう。

筆者はあまりシェア型書店には明るくない。正直その賑わいにピンときていないところがあったのだけれど、北本さんの話を聞いていくうちに、みんながシェア型書店に殺到する理由が少しわかる気がした。
現在、京都にシェア型書店は一乗寺BOOK APARTMENTの他にもこもれび書店など数店存在する。しかしそうした店舗のブースを合計したとしても、入居できる出店者の数は限られている。一乗寺BOOK APARTMENTの登場に後押しされて、京都中の本好きたちの隠れた熱気が溢れ出し、やがてシェア型書店の街と呼ばれる日も遠くないかもしれない。
3.夕書房(出版社・オープンスペース)
それぞれの物語を拾い上げるしなやかな場所

最後に紹介するのは京都市北区の夕書房。これまでの二店は書店だったが、夕書房は、本をつくる側、つまり出版社である。茨城県つくば市を拠点としていたひとり出版社で、この4月に京都に移転してきた。運営するのは高松夕佳さん。これまで文芸、アート、まちづくりといったさまざまなジャンルで活躍する人たちの営みにまつわる書籍を刊行してきた。
夕書房では金曜と土曜を中心に「文庫喫茶」として「事務所びらき」をしており土曜には刊行した書籍の著者などさまざまな人をゲストに招待する企画も行っている。「近所のおじいちゃんおばあちゃんがふらっと遊びに来てくれたり、これまでかかわってきた本の著者や編集者がおもしろがって遊びにきてくれたりして、なんだかおもしろい時間が流れます」と高松さん。
夕書房が事務所を構える場所は、もともと高松さんの祖父母の家で、幼い頃に何度も遊びにきていたという。建物自体は取り壊され土地だけになっていたところに、新たな場所をつくりだした格好だ。設計は京都の建築設計事務所・木村松本建築設計事務所。開いた居場所をつくりたいと考えた高松さんの思いを反映した、大きなガラス窓が特徴の開放的な空間が出来上がった。
お話を伺ううちに、夕書房の「文庫喫茶」という場所の魅力の本質は「夕書房の本が買えますよ」とか「コーヒーも楽しめます」ということだけではないと感じた。地域の持つ文脈を拾い上げ、周りの人の声に耳を傾け、丁寧にその場所に編み込むような、そんなしなやかさがおもしろい。
高松さんは京都に移住しこの地に根を降ろしてから、思いがけない出会いをしてきたという。「ご近所に芸術家が多いんです。数軒先の書家の先生は、御年93歳。一度お稽古を見学させていただいたのですが、先生の筆運びの美しさやお弟子さんとのやりとりがおもしろくて、気がつけば5時間が経っていました」。他にも、近隣に拠点を構えていた日本画家の作品集との出合いなど、ここに来なければなかったであろう邂逅も。この地域は大正から昭和50年代頃にかけて、日本画家の大家とその門弟が集まる場所で、芸術文化が栄えていたという。田畑が多かった当時、広い画室を構えやすかったのだろう。それから時は過ぎ、現在の周辺は民家ばかりに見えるが、過去の気配は所々にまだ残っているようだ。「これまでは社会への違和感を変革のエネルギーにする若い人たちの声を届けてきましたが、京都に住み始めたら、土地の歴史と人々の営みの蓄積がものすごくて、めちゃくちゃおもしろい。この地に流れる文化を紐解くような本づくりが始まりそうです」と高松さん。インターネットで快適になった現代、本づくりはどこでもできるものだが土地の風土や土壌によって育つ作物が違うように、住まう場所が変われば生まれる本も変わるのではないか、そんなことを感じさせる。

「お休みどころ」を目指して
京都に拠点を移し、出版社ながらオープンな場所を持つことにした高松さんが頭に思い描くのは、公民館のような場所。縁のある人や近所の人たちがやってきて、おしゃべりしたり、お茶をしたりできる場所。時には連続講座や勉強会なども行われるカルチャーセンターのような側面も持ち合わせていたいと話す。
こうした場所を志したのは、夕書房がこれまで手がけてきた本の著者の影響も大きいという。『したてやのサーカス』で語られる舞台芸術は「そこにいるだけで許された気になる」というオープンさを。『家をせおって歩いた』からは自分自身が公共性を纏うことを。そして『彼岸の図書館』からは場を開くことを。出版社だから、本に関わる仕事をしているから、という決まりきったフォーマットにおさまらない場所になりそうだ。近頃新しい出版社や本屋が増えつづけていることは何度か話したが、その目新しさも形式化されてきたきらいがある。「新しいと言われたひとり出版にもどこか『業界』ができあがってきたと感じていました。そのくくりから自由になりたくて、新天地で本屋ともブックカフェとも言い切れない、不思議な場所を始めたのかもしれません」と高松さんは振り返る。
茨木のり子の作品に「お休みどころ」という詩がある。はるか昔、一本の伸びた街道にお休みどころという旗がゆらめき、小さなベンチが置かれている。そしてそこには茶碗が伏せられ、お茶が置いてある。そんなかつての景色を懐かしむ一編である。高松さんが思い浮かべるのは「お休みどころ」に描かれる、何気なく休憩するような腰掛け、そして、なぜかふと思い出すようなそんな場所なのだろう。
今回三つの「本の場所」を巡った。新刊古書店、シェア型書店、オープンスペース、形式は三者三様だが共通して感じたのは、十分なほどに本の場所はもうすでにあるという前提の課題への意識だ。書店同士が選書を横目で見られてしまうゆえに画一化の進む書店。新刊、古書店がすでにある街。いつでもどこでも好きな本を簡単に手に入れられる時代。新しいようでいて定番化してしまったフォーマット。
既存の大きな出版業界から抜け出した「独立系」の世界も、もはや成熟しはじめている。みなさんも観光した先で出会う書店に既視感を感じる機会が多くなったのではないだろうか。筆者自身も書店主として悩みがつきない。けれど、そんな時代に生まれた新たな三つの場所は、それぞれ自分にしかない文脈を活かし、形式を越えようとする。そんな機運が高まりはじめている。京都という場所を舞台に「本の街」としての新たな姿がお目見えするのは案外近いのかもしれない。
✳︎『ポmagazine』の更新は下記からチェック!
企画編集(順不同、敬称略):光川貴浩、河井冬穂(合同会社バンクトゥ)